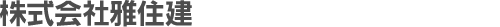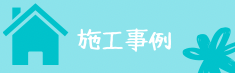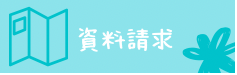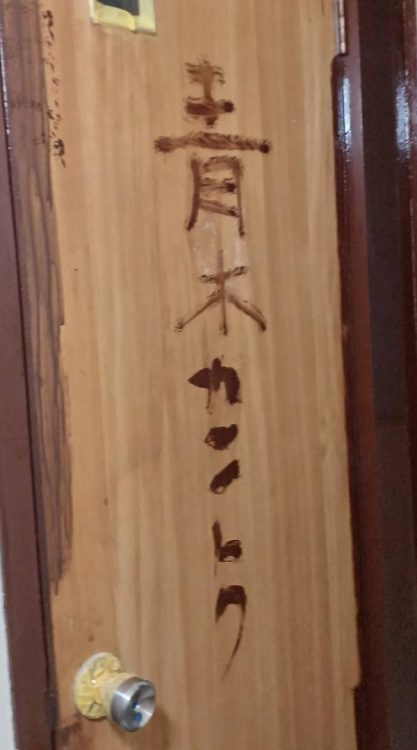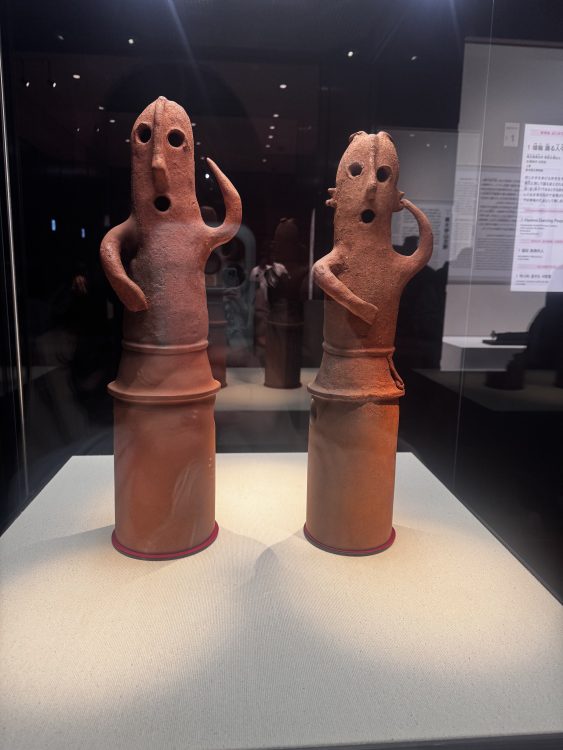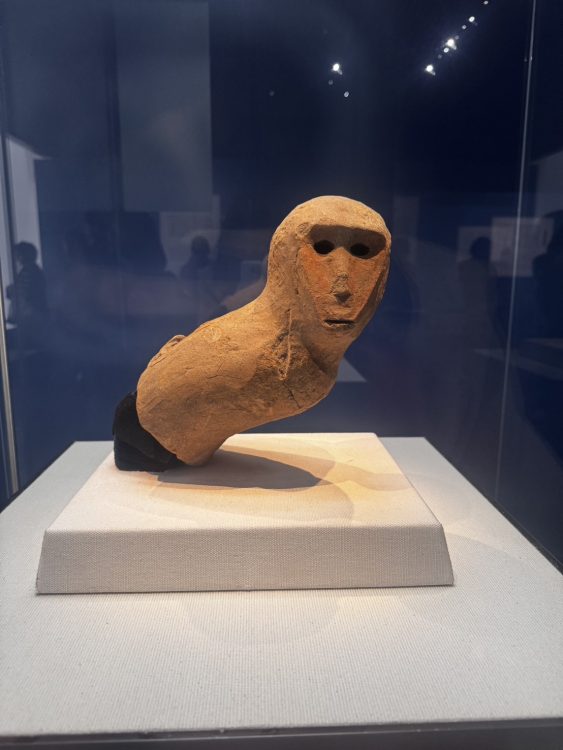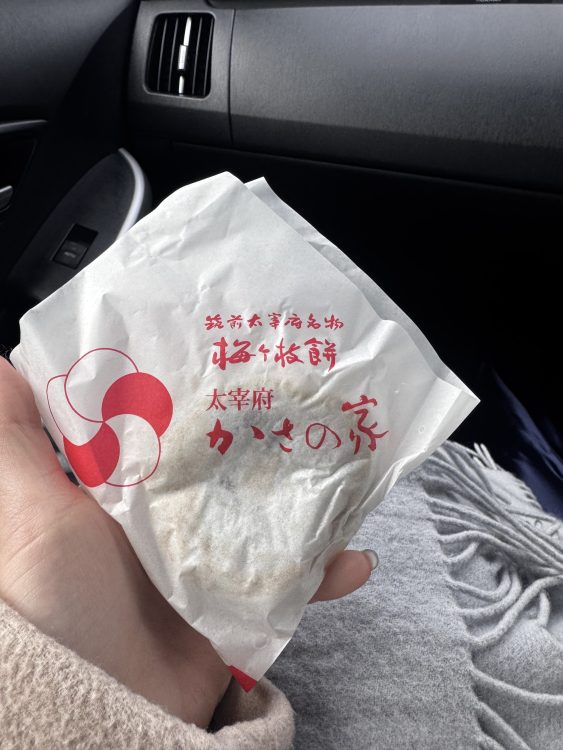こんにちは。
雅住建の松浦です^(゜Θ゜)^
だいぶ暑くなってきましたが皆様お変わりございませんか?
季節の変わり目、今から梅雨に差し掛かるので体調を崩しやすい時期に入ります。
今日は最近している身体のメンテナンスについて。
「老廃物流し(リンパマッサージ)」って知っていますか?

体内で不要になった物質をリンパマッサージによって対外に排出することで、
健康な身体を維持するための施術です。
その「老廃物流し」にはまっています!
ですがめちゃくちゃ痛いっっっ(;´Д`)💦
太ももの内側、背中の骨の周り、足首…泣き叫ぶほど痛いです(聞かせたいぐらい笑)。
そもそも「老廃物」とは私達の体にとって不必要になったもののことをいいます。
私達は、食事や呼吸などを通して体にとって必要なものを取り入れてエネルギーに変えて生活しています。
身体の中で必要なエネルギーを作り出し、不必要なものが残ります。
その不必要なものが老廃物です。
これらの老廃物が体内に溜まると、風邪をひきやすくなったり疲れが取れないなど、不調の原因となります。
老廃物を排出するために、リンパの流れを良くしたり、水分を補給したりして身体の外に老廃物を出していきます。
自律神経が乱れている方にもおススメらしいので、興味ある方は一度お試しください。
痛くないマッサージもありますよ(=゚ω゚)ノ
あとは以前から好きな「サウナ」ですね。

今はサウナーやサ活という言葉が流行っておりますが、
やはりサウナの醍醐味はサウナで汗をタップリかいた後、水風呂に入って「ととのう」時間ですね!
最高のひとときです。
この時ぐらいですかね、何も考えずにボーっとするのは。
おススメのサウナ(浴場)があればぜひ教えてください(*^-^*)
このように身体のメンテナンスは定期的にすると身体だけではなく、
心のケアもできるそうです。
そうはいってもなかなか行けない方はお家でメンテナンスをしてみませんか?
弊社でおススメしているのはパナソニックのマイクロバブル入浴「酸素美泡湯」という商品です。
「酸素美泡湯」は細かい酸素の気泡を浴槽内に発生させ、
ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで代謝を促進し、体温を高く保つことができます。
体温が上がると基礎代謝が上がり、免疫力アップというふうにつながります。
更に微細な気泡が体をマッサージし、血行を良くすることで、全身の隅々まで酸素や栄養を運び、疲労物質や老廃物の回収を促してくれます。
入浴剤や薬品を使ってないので赤ちゃんからご年配の方までご利用いただけるのも魅力ですね!
この商品はパナソニックのお風呂、全てのシリーズにつけることができます。
気になる方はお問い合わせくださいませ。
一度体験すると必ずご満足いただけます( *´艸`)
ではまた~(^_^)/